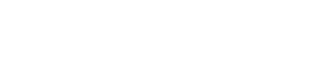本文
防災啓発・防災訓練地震に備える
家の中の安全対策
- 家の中に逃げ場としての安全な空間をつくる
部屋がいくつもある場合は、人の出入りが少ない部屋に家具をまとめて置く。無理な場合は、少しでも安全なスペースができるよう配置換えする。 - 寝室、子どもやお年寄りのいる部屋には家具を置かない
就寝中に地震に襲われると危険。子どもやお年寄り、病人などは逃げ遅れる可能性がある。 - 家具は倒れにくいように置く
家具と壁や柱の間に遊びがあると倒れやすい。家具の下に小さな板などを差し込んで、壁や柱に寄りかかるよう固定する。
畳の上に置く場合は、家具の下に板を敷く。 - 安全に避難できるように出入り口や通路にはものを置かない
玄関など出入り口までの通路に家具など倒れやすいものを置かない。
また、玄関にいろいろものを置くと、いざというときに、出入り口をふさいでしまうことも。
家の周囲の安全対策
- 屋根
屋根不安定な屋根のアンテナや、屋根瓦は補強しておく。 - 窓ガラス
飛散防止フィルムをはる。 - ベランダ
植木鉢などの整理整頓を。落ちる危険がある場所には何も置かない。 - ブロック塀・門柱
土中にしっかりとした基礎部分がないもの、鉄筋が入っていないものは危険なので補強する。ひび割れや鉄筋のさびも修理する。 - プロパンガス
ボンベを鎖でしっかり固定しておく。
非常持出品
避難するとき持ち出す最小限の必需品。あまり欲張りすぎないことが大切です。
重さの目安は男性で15kg、女性で10kg程度。背負いやすいリュックサックにまとめておきましょう。
- 携帯ラジオ
デマにまどわされないように正しい情報を得るため。小型で軽く、FMとAMの両方聴けるものがよい。予備の電池も忘れずに。 - 懐中電灯・ろうそく
停電時や夜間の移動に欠かせない。予備の電池も忘れずに。ろうそくは太くて安定のよいものを。 - ヘルメット(防災ずきん)
屋根瓦や看板などの落下物から頭部を守るため。避難路は転倒事故も多いので必ず用意を。 - 非常食・水
非常食はカンパンなど火を通さないでも食べられるもの。水はみねらるウォーターなど。赤ちゃんがいる場合は粉ミルクなども。 - 生活用品
ライター(マッチ)、ナイフ、缶切り、ティッシュ、ビニール袋など。赤ちゃんがいる場合はほ乳びんなども。 - 衣類
下着、上着、手袋、靴下、ハンカチ、タオルなど。赤ちゃんがいる場合は紙おむつなども。 - 救急用品・常備薬
ばんそうこう、ガーゼ、包帯、三角巾、消毒薬、解熱剤、胃腸薬、かぜ薬、鎮痛剤、目薬、とげ抜きなど。持病のある人は常備薬も忘れずに。 - 通帳類、証書類、印鑑
預金通帳類、健康保険証、免許証など。住所録のコピーもあると便利。 - 現金
紙幣だけでなく、公衆電話用の10円硬化も用意したい。
※非常持出品の用意のポイント
- あまり重いと避難行動に支障が出るので、重すぎる場合は飲料水などの一部を家に保管するなりして減らす。
- 重い缶詰のかわりに、比較的軽い乾燥食品などを用意する。水を注ぐだけで簡単にできる。
- できれば各自に一つのリュックを用意し、それぞれ持ち出しやすい場所に保管を。玄関先の車やトランクなどにも分散して保管しておく。
非常常備品
災害復旧までの数日間を自活するためのもの。最低でも3日分、できれば5日分を用意しましょう。
- 非常食
そのまま食べられるか、簡単な調理で食べられるもの。
アルファ米やレトルトのごはん、保存のきくパン(缶詰も市販されている)、缶詰やレトルトのおかず、インスタントラーメン、
切り餅、チョコレート、氷砂糖、梅干し、インスタント味噌汁、チーズ、調味料など。
定期的に期限を確認し、古いものから食べて、いつも新鮮なものを補充しておく。 - 水
飲料水は1人いちにち3Lが目安、ミネラルウォーターの保存期間はペットボトルで2年、缶で3~5年程度(冷暗所に置いた場合)。
随時、保存期間の確認を。さらに、生活用水の確保も忘れずに。風呂の水は次にはいるまで抜かずフタをして、
寝る前はいつもポットややかんに水を入れておく。 - 生活用品
燃料は短期間なら卓上コンロや固形燃料で十分。ガスボンベも多めに用意を。
その他、洗面具、生理用品、ビニール袋、キッチン用ラップ、新聞紙、ビニールシートなど。
※避難生活が長引く場合にあると便利なもの
なべ(コッヘル)、携帯トイレ、使い捨てカイロ、裁縫セット、雨具、ガムテープ、
地図、さらし(包帯、おしめ、手ぬぐい、ロープ、風呂敷などにも使えて便利)、筆記用具(マジックなど)、スコップ、文庫本など。
子どもがいる場合は教科書、ノートも
※阪神・淡路大震災ではこんなものが役だった!
10円玉、ドライシャンプー、ボディー洗浄剤、ホイッスル、ポリタンク、携帯コンロ、バール、常備薬、予備の眼鏡・補聴器など
※消火・救助用具も忘れずに
地震発生後の火災や家屋の倒壊などに備えて、消化器などの消化用具や、救出活動に使える工具類も準備しておく。
地震発生!そのときどうする
- まず身の安全の確保
家具などが倒れたり落下物の危険があります。机の下などに急いでもぐり込み、身の安全を確保しましょう。
激しい揺れで動けない場合は手近な布団や座布団で頭を保護します。 - すばやく火の始末
すぐに火が消せる場合は火の始末を。余裕がなければ無理をせずに身の安全を確保し、揺れの合間を見て火の始末をする。
ガス器具やストーブの火を消し、電気器具はプラグを抜く。 - 非常脱出口を確保する
地震の揺れによって建物がゆがみ、出入口が開かなくなることがあります。ドアを開けて逃げ口を確保しておく。特に中高層住宅では注意。 - 火が出たらすぐ消火を
天井に燃え移る前ならば、初期消火が可能です。「火事だ!」と大声で叫び、隣近所にも協力を求め消火に努めましょう。 - 外へ逃げるときはあわてずに
瓦や窓ガラスの落下の危険があるのでむやみに外へ飛び出さない。家屋の倒壊や火災の危険がある場合は、落下物に注意して避難する。
避難の心得 10か条
- 避難する前に、もう一度火元を確かめ、ブレーカーを切る。
- 各自が防災カードを身につける。
- ヘルメットや防災ずきんで頭を保護。
- 荷物は最小限のものに。
- 外出中の家族には連絡メモを。
- 避難は徒歩で。
- お年寄りや子どもの手はしっかり握って
- 近所の人たちと集団で、まず決められた集合場所に
- 避難場所へ移動するとき、狭い道・塀ぎわ・川べりなどは避ける。
- 避難は指定された避難場所へ。