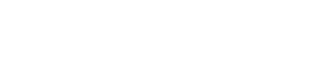本文
国民健康保険
加入する方
勤務先の保険に加入している方や他の健康保険に加入している方、生活保護を受けている方等以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
主な届け出
国民健康保険に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に届け出を行ってください。
|
このようなとき |
必要なもの | |
|---|---|---|
| 国民健康保険に加入するとき |
他市町村から転入したとき |
|
|
職場の健康保険をやめたとき |
|
|
|
子どもが生まれたとき |
|
|
|
生活保護を受けなくなったとき |
|
|
| 国民健康保険を脱退するとき | 他市町村に転出するとき |
|
| 職場の健康保険に加入したとき |
|
|
| 生活保護を受けるようになったとき |
|
|
|
死亡したとき |
|
|
| その他のとき |
住所、氏名、世帯主が変わったとき |
|
|
世帯を分けたとき |
|
|
|
資格確認書を紛失したとき |
|
|
主な給付
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
出生育児一時金 |
国民健康保険に加入している方が出産した場合、かかった費用の一部を医療機関に支払う代理受領制度があります。 | ||||
| 葬祭費 | 国民健康保険に加入している方が死亡したとき、葬儀を行った方に対し、5万円を給付します。 | ||||
| 高額医療費 |
医療費の一部負担金が下記の限度額を超えたとき、申請により超えた分の払い戻しが受けられます。(高額医療費の支給) また、資格確認書を利用している方(要申請)は医療機関へ「限度額適用認定証」(住民税非課税の方は、「限度額適用食事療養標準負担額減額認定証」)を提示することにより、病院や薬局窓口での支払いが限度額までとなります。 なお、マイナ保険証を利用している方は、上記の認定証は不要で、病院や薬局窓口での支払いが自己負担限度額となります。 |
||||
|
※入院又は、外来で高額の負担が予想される場合は、役場窓口に相談してください。 |
|||||
| ●70歳未満の方 | |||||
| 所得要件 | 区分 |
1ヶ月の限度額 |
4回目からの限度額 |
||
|
所得が901万円を超える |
(ア) |
252,600円 + 医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1% |
140,100円 | ||
|
所得が600万円を超え901万円以下 |
(イ) |
167,400円 + 医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1% |
93,000円 | ||
|
所得が210万円を超え600万円以下 |
(ウ) |
80,100円 + 医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1% |
44,400円 | ||
|
所得が210万円以下住民税非課税世帯除く |
(エ) | 57,600円 | 44,400円 | ||
| 住民税非課税世帯 | (オ) | 35,400円 | 24,600円 | ||
|
なお、1世帯で同じ月内に一部負担金を21,000円以上支払った場合が複数あり、その合計額が限度額を超えたとき、その分が支給されます。(世帯合算) |
|||||
| ●70歳以上の方 | |||||
| 所得区分 |
入院及び世帯の限度額(月額) |
||||
|
1ヶ月の限度額 |
4回目からの限度額 ☆1 |
||||
| 現役並み所得者Iii (課税所得690万円以上) |
252,600円 + 医療費が842,000円を超えた場合は、 その超えた分の1% |
140,100円 | |||
| 現役並み所得者Ii (課税所得380万円以上) |
167,400円 + 医療費が558,000円を超えた場合は、 その超えた分の1% |
93,000円 | |||
| 現役並み所得者I (課税所得145万円以上) |
80,100円 + 医療費が267,000円を超えた場合は、 その超えた分の1% |
44,400円 | |||
| 所得区分 | 外来+入院(世帯単位) | ||||
| 外来(個人単位)☆2 | 1ヶ月の限度額 3回目まで |
4回目からの限度額 ☆1 |
|||
| 一般 (課税所得145万円未満等) |
18,000円 | 57,600円 | 44,400円 | ||
| 低所得Ii | 8,000円 | 24,600円 | |||
| 低所得者I | 8,000円 | 15,000円 | |||
|
☆1 ◎過去12ヶ月間に4回以上高額医療費の支給を受けるときは、4回目から限度額が下がります。70歳未満の方や、現役並み所得者I・Ii、低所得者I・Iiの方が入院したとき「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、入院時の医療機関窓口での支払いが限度額までとなります。資格確認書をお持ちの方は、入院が決まったら申請してください。 |
|||||
|
☆2 ◎年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です(低所得者I・Iiだった月の外来の自己負担額も対象です)。 |
|||||
| 療養費 |
コルセットや治療用装具を作った場合に、保険証、医師の証明書、領収書、世帯主の預金通帳、印鑑を持参のうえ町民生活課においでください。 |
||||
| 交通事故等の被害者となった場合 |
交通事故等第三者(加害者)の行為により負傷した場合は、以下の書類をご提出ください。 人身事故証明書入手不能理由書 [PDFファイル/206KB] 交通事故など第三者(加害者)の行為により国保の被保険者が負傷をし、その治療に国保の保険を使う場合は、保険者(井川町)への届出が法令により義務づけられています。 ※ 届出書類の作成については、関与する各損害保険会社等が支援することになっておりますので、担当する損害保険会社にご相談されることをお勧めします。 |
||||
国民健康保険税
国民健康保険税は、次の方法により世帯単位で計算された額を、世帯主が納付義務者となり納めます。
| 世帯の 年間 保険税額 |
1 医療分 |
(1)所得割額(前年所得に応じて計算) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2)均等割額(国民健康保険の加入者に応じて計算) | |||||||
| (3)平等割額(一世帯当たりいくらと定額で計算) | |||||||
| 2 後期高齢者医療支援金分 |
(1)所得割額(前年所得に応じて計算) | ||||||
| (2)均等割額(国民健康保険の加入者に応じて計算) | |||||||
| (3)平等割額(一世帯当たりいくらと定額で計算) | |||||||
|
3 (40歳以上65歳未満) |
(1)所得割額(前年所得に応じて計算) | ||||||
| (2)均等割額(国民健康保険の加入者に応じて計算) | |||||||
| (3)平等割額(一世帯当たりいくらと定額で計算) | |||||||